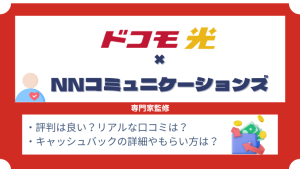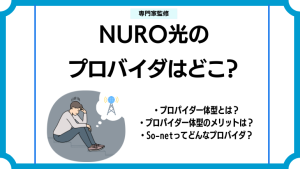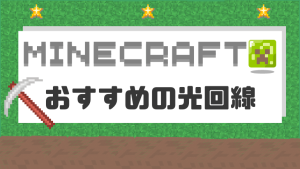「WiFiルーターに書いてある2.4GHz・5GHzってなんのこと?」「結局どっちを接続したらいいの?」と気になりこの記事にたどり着いた方へ。
結論、2.4GHz(ギガヘルツ)や5GHzというのは電波の帯域のことで、それぞれ通信速度や通信範囲などに違いがあるため、利用環境や用途によって切り替えると良いです。
この記事ではWiFiの2.4GHzと5GHzの違いや使い方、切り替え方法などを紹介していくので参考にしてください。
 小林
小林この記事を読めば家の中でより快適にネットが使えるようになりますよ!
目次
2.4GHzと5GHzの違い
Wi-Fiには2.4GHzと5GHzの2種類の電波が飛んでいて、それぞれを使いわけることで速度が速くなったり、電波が入りやすくなるといったメリットがあります。 スマホのLTEや4Gと呼ばれるものは電波の種類が違うため、2種類の電波を使いわけるといったことはできません。 基本的にはスマホやパソコンを、家のWi-Fiやモバイルルーターで接続している時に使い分けができるようになっています。 ここでは最初にWi-Fiの2.4GHzと5GHzの違いについて詳しく説明していきます。
2.4GHz|通信範囲が広いが電波の干渉を受けやすい
2.4GHzは通信範囲が広く、ルーターから離れた所でも電波が届きやすいのが特徴です。
また壁や床などの障害物にも強いため、2階や仕切りのある部屋などでもWi-Fiに接続してネットを使うことができるようになります。
ただし、2.4GHzは家電やBluetoothでも使用されている電波のため、電波の干渉が発生しやすくなっています。
特に電子レンジの電波と干渉しやすいようで、電波の干渉が起こると回線速度が遅くなり、動画や写真の読み込みが遅くなる傾向があります。



電波が届きやすい分速度が遅くなってしまうことがあるので、建物の状況やネットの使い方によってはこのあと解説する5GHzを利用した方がいい場合が多いよ!
5GHz|通信範囲は狭いが速度が安定しやすい
一方5GHzの電波に関しては届く範囲が狭く、壁や床といった障害物にも弱いため、2.4GHzに比べるとルーターから離れたところでは使いにくい電波となっています。
ただし5GHzは電波が強力なので回線速度が速く、電波干渉にも強いのが特徴です。通信速度の速さや安定性が求められる動画やゲームなどに向いている電波といえるでしょう。
また、5GHzはWi-Fiルーターやモバイルルーターなど、ネットを利用するため専用機器のみで使われている電波なので、干渉も少なくなっています。
仮に家の周りで5GHzの電波がたくさん飛んでいたとしても、先ほども紹介した通り電波が強力なので、干渉することもほとんどありません。



広い部屋での利用には不向きな電波ですが、速度を速くしたい時に役立つのが5GHzの電波ですね。
2.4GHzと5GHzの使い分け方
WiFiの2.4GHzと5GHzの違いはわかったけど、結局は日常生活でどのように使い分けたら良いかわからないことが多いと思います。 状況によって自分で上手に切り替えをするのが1番ですが、何度も切り替えをするのは面倒です。そこで、2.4GHzと5GHzの基本的な使い分けの方法について紹介していきます。
基本は5GHzを利用すると良い
WiFiには2.4GHzと5GHzの2つの電波が飛んでいますが、基本的には5GHzの電波を利用するようにしましょう。5GHzの方が干渉も少なく、速度も速くなりやすいので動画やゲームなども快適に利用できるからです。
5GHzは電波が届かないというデメリットもありますが、建物の構造や間取りによっては5GHzでも問題なくWi-Fiが届くことも多くなっています。



特に、Wi-Fiルーターやモバイルルーターなどの近くでネットを利用する場合や、ワンルームなど狭い部屋であれば5GHzで十分でしょう!



2階や仕切りがある部屋は電波が届きにくいですが、とりあえず5GHzに接続してWi-Fiが使えるかどうかを試してみましょう。
5GHzが繋がらない時は2.4GHzに切り替える
5GHzでネットが繋がらない、速度が遅くなる時は、ネットを利用している建物の構造や間取りが5GHzに適していないと考えられます。 そのような時は電波の範囲が広くて、障害にも強い2.4GHzに切り替えましょう。 速度が遅くなってしまうこともありますが、それでも動画や検索くらいであれば問題なくできることも多いです。 ただし、2.4GHzでオンラインゲームをすると、ラグの発生や接続が切れるといった恐れもあります。ゲームはできるだけ5GHzを利用することをおすすめします。
あわせて読みたい




Wi-Fiが届かないときの対処法まとめ📶2階は中継器が必要?
家の中でWi-Fiが届かない場所があって困っていませんか? Wi-Fiルーターの設置場所から離れた寝室や浴室、2階などではWi-Fiが届きづらく、通信速度が遅くなることも。 ...
2.4GHzしか接続できない機器もあるので注意
最近は家電やプリンターなどもWi-Fiに繋げられるようになりました。ただし家電の場合、2.4GHzしか接続できないこともあるので注意してください。 特に5年以上の前の家電だと2.4GHzにしか接続できないことも多いみたいですが、家電の場合は速度やWi-Fiの安定性は必要ないので2.4GHzでも十分です。



パソコンやスマホの場合はほとんどが5GHzにも対応しているため、気にしなくてOKだよ!
2.4GHzと5GHzを切り替える方法
ここではWiFiの2.4GHzと5GHzを切り替える方法について紹介していきます。 Wi-Fiルーターとモバイルルーター(ホームルーターやポケット型Wi-Fi)によって切り替え方法に違いがありますので注意してください。
WiFiルーターでの切り替え方
光回線やケーブルテレビでインターネットを利用している場合は、Wi-Fiルーターが設置されているはずです。ほとんどのWi-Fiルーターはすでに2.4GHzと5GHzのWi-Fiを同時に出しています。
そのため切り替えをする場合はスマホやパソコン側で設定をすることで、電波の切り替えができるようになります。
スマホやパソコンのWi-Fiを設定する画面で、同じIDで「〇〇〇〇〇ー2G」、「〇〇〇〇〇ー5G」の2種類のWi-Fiを選択することができるようになっています。
「〇〇〇〇〇ー2G」は2.4GHz、「〇〇〇〇〇ー5G」は5GHzにそれぞれ対応していますので、接続し直すことで簡単に切り替えができます。(パスワードの再入力が必要な場合もあります。)



また2.4GHzと5GHzの両方が使えるゲーム機や家電でも、同じような方法で切り替えができますので、試してみてください。
モバイルルーターでの切り替え方
モバイルルーターを利用している場合は端末で設定をして、2.4GHzと5GHzのどちらの電波を飛ばすのかを選ぶことができます。 端末で2.4GHzと5GHzの切り替えをしたあとに、パソコンやスマホでWi-Fiに繋ぐと電波を使い分けることができるようになります。 機器にもよって細かい設定方法に違いがありますが、ここではモバイルルーターでも人気なWiMAXでの切り替え方法を紹介してきます。
▼切り替え方法
1.「設定」をタップ
2.「LAN側設定」をタップ
3.「Wi-Fi設定」をタップ
4.2.4GHzや5GHzを選択
電波の切り替えをしても速度や接続が改善されない時はモバイルルーターを置いている位置が悪い、距離が遠いといったことも考えられます。 モバイルルーターは持ち運びができるので、スマホやパソコンの近くに置いてネットを利用するようにしてみてください。
自動切り替えにする方法も
Wi-Fiの2.4GHzと5GHzは自分で切り替えをする必要がありますが、下記のように自動で切り替えをしてくれるような方法もあります。 ・バンドステアリング機能を利用する ・メッシュWiFiを利用する 建物や周辺の電波の状況に合わせて、繋がりやすいWi-Fiに自動で切り替えをしてくれます。
バンドステアリング機能を利用する
バンドステアリング機能とは周辺の電波状況に合わせて、繋がりやすい電波を選んで自動的に選んでくれる機能です。例えば、2.4GHzの電波が増えて干渉する可能性が高くなると、電波が少ない5GHzへ自動的に切り替えをしてくれます。 特にWi-Fiルーターの場合はバンドステアリング機能がもともと備わっていることが多く、自動的に切り替えをしてくれていることも多いです。 自分が使っているWi-Fiルーターを調べればバンドステアリング機能があるかどうかを確認することができるので、気になる人はチェックしてみましょう。



Wi-Fiルーターの設定を変更すれば、バンドステアリング機能をOFFにできる機種もあるよ!
WiMAXでバンドステアリングを利用する方法
WiMAXの最新機種である「WiMAX06」でもバンドステアリング機能を利用することができるため、何度も切り替え設定をする必要がありません。
▼変更方法
1.設定をタップ
2.LAN側設定をタップ
3.Wi-Fi周波数設定をタップ
4.2.4G/5G同時にチェック
5.「はい」を選択する
または「クイックメニュー」→から「Wi-Fi周波数」を選択し「2.4G/5G同時」にチェック、その後に「はい」をタップするとバンドステアリング機能が作動します。 バンドステアリング機能にする場合は「2.4G/5G同時」のチェックをはずしましょう。
メッシュWiFiを利用する
メッシュWi-Fiはメインのルーターとサテライトルーターという子機のようなルーターを、部屋の中にいくつか設置することで建物全体にWi-Fiの電波を飛ばせるようになる機能です。 そのため、2階や別の部屋などにも電波が届きやすくなるメリットがあります。 このメッシュWi-Fiもバントステアリングと同じように自動的に繋がりやすい方を厳選して、勝手に繋いでくれる機能を持っているため、常に状態のいい電波を利用することができるようになります。 メッシュWi-Fiはメインルーターやサテライトルーターなど、いくつか機器を揃えないといけないので費用がかかってしまいますが、かなりいいWi-Fiの環境を構築することができるようになるでしょう。
WiFiの2.4GHzと5GHzについてよくある疑問
周辺の電波を確認する方法は?
WiFi Analyzerというソフトやアプリを使うと、2.4Hzや5Hzの電波がどれくらい飛んでいるのかを確認することができます。 またMacbookAirのワイヤレス診断のように元々アプリが入っているケースもあります。下記の写真は自宅で電波を確認した時の写真です。


写真に映っている総計が、2.4GHzと5Hzの電波の合計です。合計で23本飛んでおり、そのうち2.4GHzが16本、5Hzが7本飛んでいることがわかります。 先程も紹介した通り2.4GHzの電波はたくさん飛んでいるため干渉のリスクが高く、一方で5GHzは少ないので電波の干渉は少ないでしょう。 これらのアプリやソフトを使って、家の電波状況を確認しながら2.4GHzと5GHzの電波の接続を使いわける判断をしてください。
Wi-Fiの規格とは?
Wi-Fiにはいくつか規格があり、それによって利用できる電波の種類に違いがあります。
| 規格 | 電波の種類 |
|---|---|
| IEEE 802.11ax | 2.4GHz/5GHz |
| IEEE 802.11ac | 5GHz |
| IEEE 802.11n | 2.4GHz/5GHz |
| IEEE 802.11g | 2.4GHz |
| IEEE 802.11a | 5GHz |
現在最も普及しているのは最新の「IEEE 802.11ax」または「IEEE 802.11ac」という規格です。Wi-Fiルーターやモバイルルーターで「IEEE 802.11n」の規格に対応していものは、2.4GHzと5GHzの切り替えができるようになっています。 これからWi-Fiを購入する方は、最新規格の「IEEE 802.11ax(Wi-Fi6)」を選ぶことをおすすめします。
まとめ
2.4GHzと5GHzはそれぞれ特徴があるため、利用環境や用途によって切り替えをして使っていくのがおすすめです。切り替えるのが大変な場合はとりあず5GHzを利用して、必要なときに2.4GHzへ切り替えるのがいいでしょう。 またバンドステアリング機能やメッシュWi-Fiを利用することで、自動的に切り替えをしてくれるようなネット環境をつくることもできるので、検討してみてください。